 ・実際に政治や社会的活動されている方
・実際に政治や社会的活動されている方
・SNSで政治や社会への主義主張書かずにいられない方
・大衆への迎合でなく、独自色の強い政治、社会的意見をお持ちの方これらいずれか条件に当てはまる方は、
(寄付金等は別にして)
自分でお金を用意する、稼ぐなら、ビジネスより投資が向いている、
と言う件について書いていきます。
<政治や社会の主義主張が強いとビジネスは難しい>
私自身の事や、SNS上の人を見てきて感じた事。
それは、
政治や社会に対する主張が強い人は、ビジネスに向いてないと言うことです。
投資が向いている、以上に、
ビジネスに向いてない、
が当てはまります。
政治や社会への主義主張が強いとビジネスで稼げない、
これは、以下の2つの理由があるからです。
理由①:政治・社会への主義主張が強い人は、ものの見方が独自すぎる
政治や社会への主義主張が強い人は、
何事に対しても、
他の人とは違う、独自の視点を持っている事が多いです。
この、独自の視点と言うのは、
一定の範囲内、
ある共通の基盤の範囲内であれば、
強みとなりますが、
政治や社会への主義主張が強いタイプの人は、
他の人と共通の基盤さえ持っていない、
思考タイプが根本的に異なっている場合が多いです。
こうなってしまうと、
ただ周りからずれているだけになってしまい、
一般の人向けのことをやっても、共感されにくいです。
また、政治や社会への主義主張が強い人は、
何事に対しても、
主義主張、つまり、言ってる内容で考え、判断する事が当たり前になってます。
このため、いい事を言えば、
素晴らしい主張をすれば、
相手は動いてくれる、と、無自覚に考える傾向があります。
しかし、世の中のほとんどの人は、
言ってる内容よりも、
「誰が言ってるか」
で判断しています。
このため、
「素晴らしい事を言っている」と言うプラスの評価より、
「よく分からない人がよく分からない事を言っている」と、
マイナスに評価されてしまいがちです。
理由②:周りの人は、あなたと関わってあなたと同じ思想の持ち主と思われたくない
これは本当におかしな話なのですが、
最近の風潮として、
「ある人の活動を支持する=その人と同じ思想の持ち主」
と勝手に決めつける人が少なからずいます。
これだけだと何の話か分からないので、
具体例を出します。
2019年8月のあいちトリエンナーレ・表現の不自由展
で、
昭和天皇の肖像画を燃やしたとも受け取れる作品が出展されました。
このイベントは、愛知県の施設で開催されましたが、
ただ会場を貸し出しただけの大村愛知県知事や、
その後起きた賛否両論の中で、
大村知事や表現の不自由展を支持しただけで、
あいつは昭和天皇の肖像画を燃やす事に賛成の人、
と決めつける声が、少なからず出たのです。
大村知事はじめ、ほとんどの人は、
彼らの主義主張には賛同しないが、
彼らにも表現の自由はある、
と考えただけにもかかわらず、です。
しかも困った事に、勝手な決めつけする人に限って、
あいつは売国奴、のようなレッテルをばらまいたんですね。
政治や社会への主義主張が強い人と関わると、
これと似た形で、言われなき非難を受けるリスクがあります。
そのため、政治や社会への主義主張が強い人が、
コミュニティビジネスの場合はもちろん、
単にサイトアフィリエイトしただけでも、
読者側が、そういう人のサイトと言うだけで、
無意識に遠ざかってしまい、
政治や社会への主義主張が強い人のビジネスは、売れないのです。
スポンサーサイト
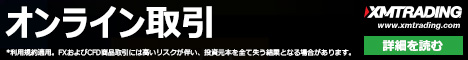
<政治や社会への主義主張するにもお金が必要>
しかし、当たり前のことですが、
政治や社会への主義主張を続けるにも、お金は必要です。
お金がなければ、主義主張どころか、
日々の生活さえ、ままならなくなってしまいます。
ですから、当然ながら、
政治や社会への主義主張する人も、
何らかの形で、お金を集め続ける必要があります。
<政治や社会への主義主張が強い人は、投資をしている>
では、
実際に政治活動をしていたり、
ネット上で政治や社会問題の配信している人が、
どのような形で資金運用しているか?
調べてみたところ、
FXや株、と言った、投資をされている方が多かったです。
半面、政治や社会活動の傍らでサイトアフィリエイトをして、
成果を出せている、と言う方は、
私が調べた範囲内では、見当たりませんでした。
既に活動されている方が、ビジネスより投資を選択している以上、
ネットビジネスしながら、
政治や社会に対する意見も同時にどんどん発信していきたい、
と言う方には、
やはり、ビジネスよりも、投資が向いています。<実際に政治活動されている方にも注目されたFX会社>
実を言うと、私に対して、
政治活動されている一方で、
(活動資金のため?)資産運用にも興味ある、と言う方から、
XMと言うFX会社について、問い合わせがきたことがあります。
デリケートな部分に口出しする以上、
国内で資産運用をしたくなかったのかもしれません。(そう言えば、TVニュースで取り上げられる政治家にも、
海外で資産運用、と言うケースは、よくありますね。)
また、海外FXは、政治的背景を抜きにしても、
・少額資金からハイレバレッジで運用できる
・ゼロカット導入で、入金額以上の損失リスクがないと言う、国内FXや他の投資にはないメリットがあります。
そして、数多くある海外FXの中でも、
XMは、実績に定評のあるFX会社です。
・資産運用にかける時間は最小限にして、なるべく政治や社会活動に時間をあてたい
・少額資金を効率よく増やして活動費に回したい
・運用に失敗しても、借金抱えて活動も生活もできなくなる事態は避けたい
・詐欺被害にも遭いたくないこれらの条件を満たすなら、
以下のバナーからXMで口座開設して、
FXで活動資金を増やしていくことをお勧めします。
FX会社は事実上、XM一択時代になりました、クリックして口座開設!
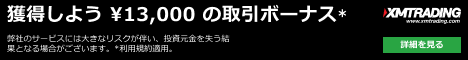
※XMの口座開設方法は、
XMのFX口座開設方法を教えますに書いた通りです。
スポンサーサイト

